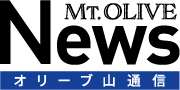トランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領のホワイトハウスでの口論については、日本のメディアもいっせいに報じている。
President Donald J. Trump and Vice President JD Vance put AMERICA FIRST. pic.twitter.com/AkAvzKpcpb
— The White House (@WhiteHouse) February 28, 2025
両首脳の決裂の後、今、イギリスとフランスが中心となり、ウクライナの安全保障に協力しようとするヨーロッパの国々とで、停戦案を模索している。その結果をアメリカに持ち込んで、協力を打診するとみられている。しかし、アメリカは、すでに、ウクライナへの武器支援停止の検討に入っていると伝えられている。
この口論については、現状を率直に分析して、どうするかを考えようとするトランプ大統領に対し、戦争の当事者であるゼレンスキー大統領は、そこまで割り切れないのだろうと思った。
戦争はすでに3年を経過したが、一向に終わる気配がない。大国であるロシアに対し、ウクライナは外国の、特にアメリカの支援がなければ、勝てる見込みはない。ということは、アメリカがこの戦争を続けているようなものなのだとトランプ大統領は考えている。
ウクライナが基本的に求めるのは、ロシアが撤退することである。しかし、戦争が3年経った今の現状を見ると、もし、アメリカが、ブーツオンザグランド(軍の派遣)に踏み切り、フルでロシアと戦えば、もしかしたら、その可能性があるのかもしれない。しかし、それは第三次世界大戦を意味する。
もちろん、アメリカにその気は全くない。となれば、もう勝つ見込みがない戦争に、これ以上支援しても、人が死ぬだけで、意味はないとトランプ大統領は主張する。今は、ロシアに多少、譲歩してでも交渉で、将来にむけたよりよい条件を目指す方がよいとトランプ大統領は言っているのである。
しかし、戦争の当事者であるゼレンスキー大統領としては、そこまで割り切れない。そんな不条理があってはならないのである。もともとロシアが侵攻してきたことが原因であるのに、そのロシアが、なんの懲罰もないのはおかしい。将来の国際情勢のルールの崩壊にもつながる。これもまた、正しい主張である。
しかし、報道によると、今回、ゼレンスキー大統領は、トランプ大統領が言うように、ロシアの残留を認めるしかないと考えていたようであった。しかし、その場合は、安全保障をアメリカに約束してもらいたいと訴えていた。それが口論で、破綻したということである。
私たちはここから何を学ばなければならないのだろうか。それは、これからは自分の正義は言うまでもなく、いわゆる正論にもとらわれず、実質はどうなのかにも目を向けなければならない時代に突入したということである。
どういうことかというと、「世に不条理はある」である。不条理にこだわるのではなく、その現状を直視して、今何をしなければならないかに集中する。
できるだけ起こりうる結果も考え尽くして行動に出るが、それでも悪い結果が出ることもある。その時は、またその時点で、そこから対処する。これが、ユダヤ人とその国、イスラエルが、長い苦難の歴史の中で、先に学ばされてきたことである。
あともう一点は、自分のことは自分で守るという原則である。
イスラエルとアメリカは友好国である。しかし、その関係は、イスラエルは、アメリカに武器支援はしてもらうが、実際に戦うのはイスラエル自身であるという原則に基づいている。何かあっても、アメリカが軍を派遣してイスラエルを助けにくることはない。イスラエルはこれを十分に理解している。
無論、ゼレンスキー大統領に、アメリカにそんな期待はまったくないだろう。そんなことを言うことも失礼であることと思う。
しかし、現実は、アメリカ軍が一緒に戦わないと、兵力においてもロシアに勝てるみこみがないということは、厳しいながら、現状かもしれない。それは、イギリスやフランスもわかっているのではないかと思われる。
これからゼレンスキー大統領は、難しい決断をせまられる。日本も例外ではなく、世界がこの現状に向かいあわなければならないだろう。
なお、イスラエルのメディアは、自分のことで忙しすぎるのか、この件については、ニュースサイトからはすぐに消えてしまっていた。